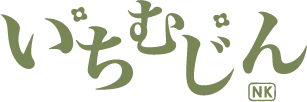News
-

2024.09.18
新しく「プライベートナース」紹介ページを公開しました。
-

2024.07.05
いちむじん+にて、7月24日(水)10:00~12:00の日時で参加無料の「リハビリ体験」を行います。
-

2023.12.27
「株式会社NKプランニング」のサイトが公開されました。
-

2023.11.21
「訪問看護ステーションいちむじん高知」のサイトが公開されました。
-

2023.10.02
秋バテに注意‼️
今年は残暑が長く、朝晩の気温がようやく下がり、秋を感じられるようになりました。季節の変わり目は、昼夜気温の変化が大きく体調を崩しやすい季節です。夏の疲れが体に残っている時期なので、食欲不振や倦怠感など秋バテの症状が出てくる事もあります。
特に高齢者の方は、体温を調整する機能が低下してくるので、注意が必要です。
『体調管理で気をつけるポイント』をご紹介したいと思います。
⚫︎1日3食バランスよく食べる
⚫︎体温調節ができる服装を選ぶ
(上に羽織れるものやスカーフなど)
⚫︎適度な運動で血流アップ
(ウォーキングなど)
⚫︎ゆっくりと入浴する
⚫︎睡眠をしっかりとる
次に…『秋バテ予防となる食材』
をご紹介いたします。
◇根菜類・イモ類
エネルギー源であるでんぷん等の糖質が豊富で、里芋には高血圧予防効果が期待できるカリウムが豊富に含まれています。れんこんはビタミンCや食物繊維が豊富。
根菜は体を温める効果があると言われているので、冷え対策に効果が期待できます。
◇きのこ類
腸内環境を整える食物繊維、ビタミン類やカリウムも豊富。
しいたけ・しめじに多く含まれるビタミンDは免疫力アップ効果があります。
まいたけにはビタミンやミネラルに加えて、免疫力を高めるβグルカンが豊富に含まれています。
◇さんま
不飽和脂肪酸の一種DHAやEPAが豊富で、動脈硬化や貧血予防に効果的です。
◇豚肉
疲労回復効果が期待できるビタミンB1が多く含まれています。玉葱やにんにく、ニラなどに含まれる「硫化アリル」はビタミンB1と協力して糖質をエネルギーに変え、疲労回復を助ける効果があるため、一緒に食べると更に効果が期待できます。
上記のような旬の食材を食べ、規則正しい生活を送り、秋バテにならないように注意しましょう。
-

2023.09.28
新しく「いちむじん+」紹介ページを公開しました。
-

2023.09.28
ホームページリニューアルのお知らせ
日頃より、いちむじん訪問看護ステーションのホームページをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、弊社ホームページを、より使いやすく、わかりやすく、デザインを全面的にリニューアルいたしました。
今後もコンテンツの充実に努めて参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
-

2023.09.01
夏の運動のすヽめ
"基礎代謝"は一般的に『夏は低く冬に高い』といわれています。基礎代謝が低い夏は、身体活動や運動を習慣化し、エネルギー効率を上げましょう。
◼️夏の運動の注意点
夏の運動は脱水・熱中症に注意が必要です。
以下に注意した上で、運動を行いましょう。
①こまめな水分・塩分補給
運動を行う前にまずコップ1杯以上の水分を摂り、運動中・運動後も水分を摂るようにしましょう。血液中に含まれる電解質成分も汗となって身体から失われます。塩分は特に多く出ていってしまうので、水分と共に塩分の補給も必要です。
高齢の方は、喉が渇いたという感覚や汗をかく機能が低下します。汗をかいていなかったり、喉が渇いていなくても、こまめな水分補給を心掛けましょう。
②体温を下げる工夫
「汗」は、身体の熱を外に逃がして、体温を一定に保つ役割を果たしています。
しかし湿度が高いと、暑くても汗をかきにくくなります。汗をかかないと身体の熱がこもりやすくなるので、シャワーを浴びる・水に濡らしたタオルで身体を拭くなど、体温を下げる工夫が必要です。
③体調管理
運動を行う日は、朝食・昼食をしっかり摂りましょう。また日頃から、栄養バランスの整った食事を3食摂り、疲れにくい身体をつくっておきましょう。
また、睡眠不足にもならないように、しっかりと睡眠をとることも大切です。
④高温環境における運動中の熱中症予防
・服装は薄着で通気性の良いものにする。
・運動開始前に体調不良(睡眠不足・風邪気味・下痢)などであれば、運動は中止する。
・運動はいつもより軽め、短時間で休憩をとる。
・休憩と水分補給は気温28℃以上では30分毎
気温31℃以上では10〜15分毎に行うのが目安。
・気温35℃以上では、全ての運動療法を中止する。
・室内でも冷房のない部屋では熱中症に注意が必要。ただし冷房が効いた部屋での運動は可能。
・運動開始後に気分不良やめまいを感じたら、すぐに運動をやめる。
★運動習慣がない人は汗をかきにくく、身体の中に熱がこもりやすくなります。運動をする習慣を身につけて汗をかきやすい身体をつくるようにしましょう。
-

2023.08.02
いちむじん訪問看護ステーション高知 管理者ご挨拶
いちむじん訪問看護ステーション高知の新しい管理者として令和5年7月1日より、
近藤由三(こんどうゆみ)が就任いたしました。利用者様ひとりひとりを大切に「心暖まる看護」を心掛けて、サービスの提供をして参ります。
今後とも引き続きご愛顧の程、よろしくお願いいたします。医療現場で長年、小児看護に携わらせて頂き、患者様が出生から様々な状態を乗り越え、ご家族と看護師がお家での生活を見据えながら想定される不安を軽減し、安心して退院されていくところを一緒に経験してきました。その経験を元に患者様やそのご家族への思いを大切にしながらご自宅での生活に少しでも不安が少なくなるよう訪問看護に携わっていきたいと思っています。
生活環境に応じた適切なケアの提供に対応するため、医師や介護スタッフ、ケアマネージャーと連携を取り、その人らしい療養生活を提案します。その体制を整え、24時間365日の対応をお約束することで、「家族の一員」として頼っていただけると信じ、訪問看護に携わっています。
「家族の一員」として、「頼りになる存在」であり、「人と人」として向き合う。そうすることで、満足していただける在宅ケアが提供できると確信しています。
訪問看護をお考えの方は、ぜひ、お話をお聞かせください。
-

2023.08.01
8月、いよいよ夏本番。
- 暑い日が続き…
『全身の疲労感・食欲不振・無気力』など
夏バテ症状が出ている方も多いのではないでしょうか?
夏バテ症状を改善するには
・身体の疲労回復をしっかり行うこと
・自律神経が集まり、免疫の要でもある腸を整えることが大切です。
そこで意識したいのが食事と睡眠。
✔︎食事
食欲のない夏は、さっぱりとした冷たい麺類などが多くなります。しかしこれは、胃腸が冷えると同時に、糖質の多い食事となり、糖質をエネルギーに変えるビタミンB1が不足しがちになります。
※ビタミンB1が不足すると、活動や回復に必須のエネルギーが作れなくなって疲労感が増し、夏バテの症状を悪化させてしまいます。
良質なタンパク質・高エネルギー・高ビタミンの食材を積極的に摂取し、栄養のバランスを重視した食事を心がけましょう。
▶︎(ビタミンB1が多く含まれる食品)
豚肉、ウナギ、レバー、子持ちカレイ、紅サケ、玄米、豆腐、さつまいも、そば、マカロニなど
✔︎睡眠
寝苦しい夜はつい、エアコンに頼りがち。
設定温度を下げ過ぎると身体を冷やし過ぎてしまい、だるくなったり夏バテにつながります。 (さらに…)
Warning: Undefined variable $additional_loop in /home/tomoju/ichimujin-nk.com/public_html/mg/wp-content/themes/ichimujin2023/archive.php on line 24
Warning: Attempt to read property "max_num_pages" on null in /home/tomoju/ichimujin-nk.com/public_html/mg/wp-content/themes/ichimujin2023/archive.php on line 24